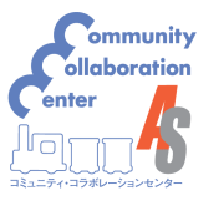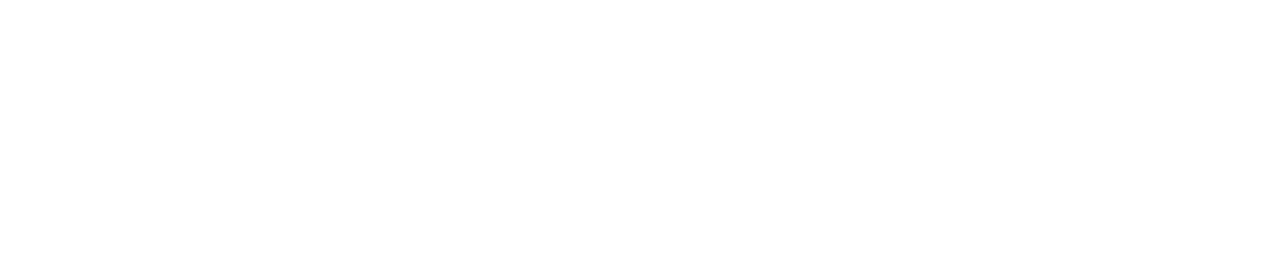

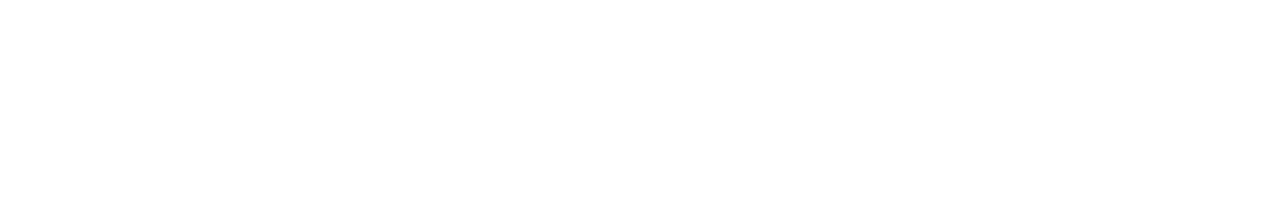
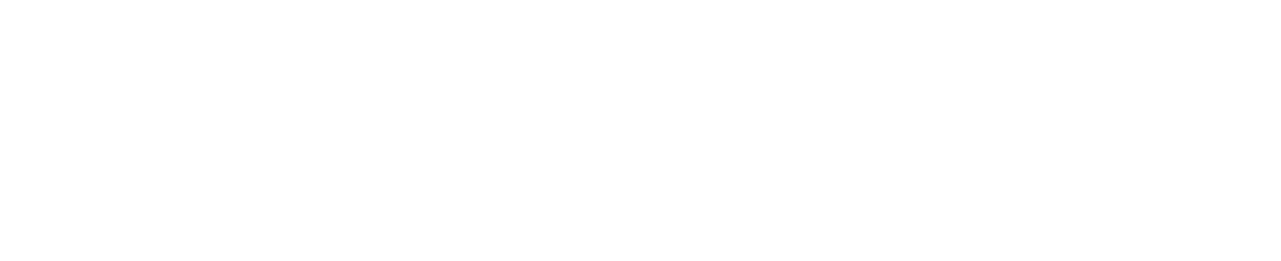



2025年度CCC開設科目
教育(カリキュラム)
地域へ、未来へ、走り出す。
自ら考え行動する力を育みます。
CCCでは卒業認定単位であるCCC開設科目を開講しています。ボランティアはもちろん、社会で活躍するうえで必要な力、生きていく上で必要な力を身につけることのできる科目を準備しています。これらの講義は社会で役立つスキルを学ぶ内容で、現時点で「ボランティア」に関心のないあなたにとっても役立つはずです。授業を通じて、みなさんが自ら考え、行動する力を向上させることを応援します。履修がまだの人はぜひ履修してみてくださいね!
知識系
ボランティア ※2024年度
梅原 聡 先生、岡田 守弘 先生
授業「ボランティア」はボランティア活動経験の有無にかかわらず、ボランティア活動や地域・社会貢献活動に関心がある学生、また「何かやってみたい」と考えている学生に向けて開講している入門科目です。授業においては、ボランティアに関する基本的な知識についてのレクチャーのほか、地域・社会が抱える課題解決のためにボランティア活動がどのような役割を担うことができるのかについてワークショップ形式で理解を深める機会をもちました。また複数の外部ゲスト講師を招くなどして実際の活動事例を紹介し、活動者の人生を形作るものとしてのボランティア活動の意義についても扱いました。受講生からは、地域や社会のため、そして自分のためなど、ボランティア活動が有する柔軟かつ多面的な「顔」に触れるなかで、受講生自身にとっての「ボランティア」を探り、意味付ける15回となった旨が受講後の感想として多く寄せられました。また授業が進むにつれて、ボランティア活動に参加した受講生の経験談が教室に集まるようになり、いつしか授業の場が他の受講生の第一歩を応援・歓迎し、それぞれの一歩から学び合うコミュニティともなっていたことはとても印象的です。教室で飛び交うリアリティを伴う言葉や、そのはつらつとした姿に、私自身も活力をいただいていました。

文学部 2年 間宮 菜月
スキル系
実践系
キズナプロジェクトB ※2024年度
岡田 守弘 先生
この授業は、地域やNPO と連携し実際に活動をおこなうプロジェクト型の演習科目です。学生がプロジェクトの立案から振り返りまでの実践を通して学び、授業後も主体的な活動ができるような基礎力や実行力を身につけることを目標としています。
さまざまな学部や学年の学生が履修するため、授業は学生同士のチーム作りから始まり、社会課題の情報収集や現地へのフィールドワークを経て、プロジェクトを組み立てます。2023年度は、特定非営利活動法人こどもNPO様と連携し、「名古屋市ひとり親家庭の子ども居場所づくり事業」に参加している子どもたちとの交流活動をおこないました。事前に関連情報を調べて知るだけでなく、学生たちがそれらを知ったことで得た印象や直接現地へ赴き見聞きすること、そして事前の印象と現状から感じたギャップも大切にしながら、授業を進めました。連携先の方々の社会課題に向き合う姿勢や価値観から、多くを学ぶ履修生の姿が印象的でした。
子どもたちの置かれる現状や私たちの活動に対して、細やかなところまで気持ちを寄せてもらったことが、実際に企画実施する際に活きていたなと感じます。生活困窮状態に置かれる子どもたちにとって、活動の場や関わりを通じて感じる安心感や充実感が、この先の人生に大きな変化をもたらす一助になります。子どもたちの気持ちや言葉を正面から受け止め、対等に関わっていく姿は素晴らしいものがありました。
特定非営利活動法人こどもNPO副理事長
山田 恭平様
交流文化学部 3年 中村 智華
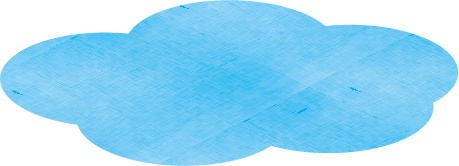
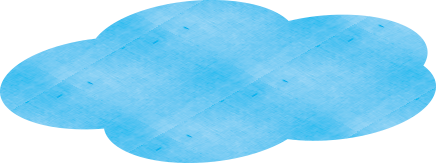
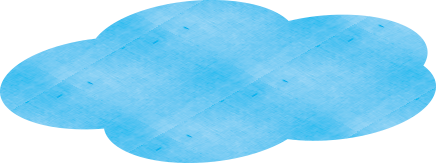
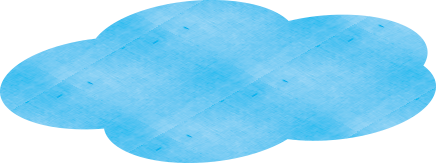
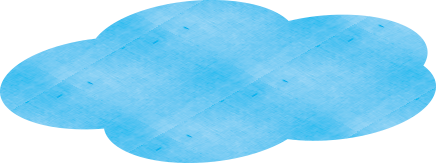
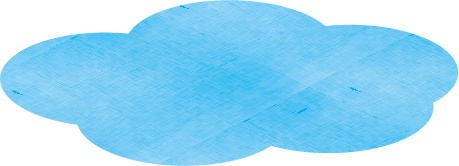
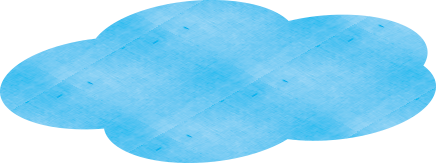
Copyright © AS University. All Right Reserved.